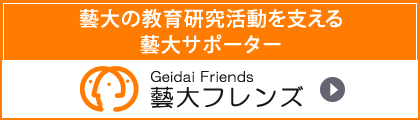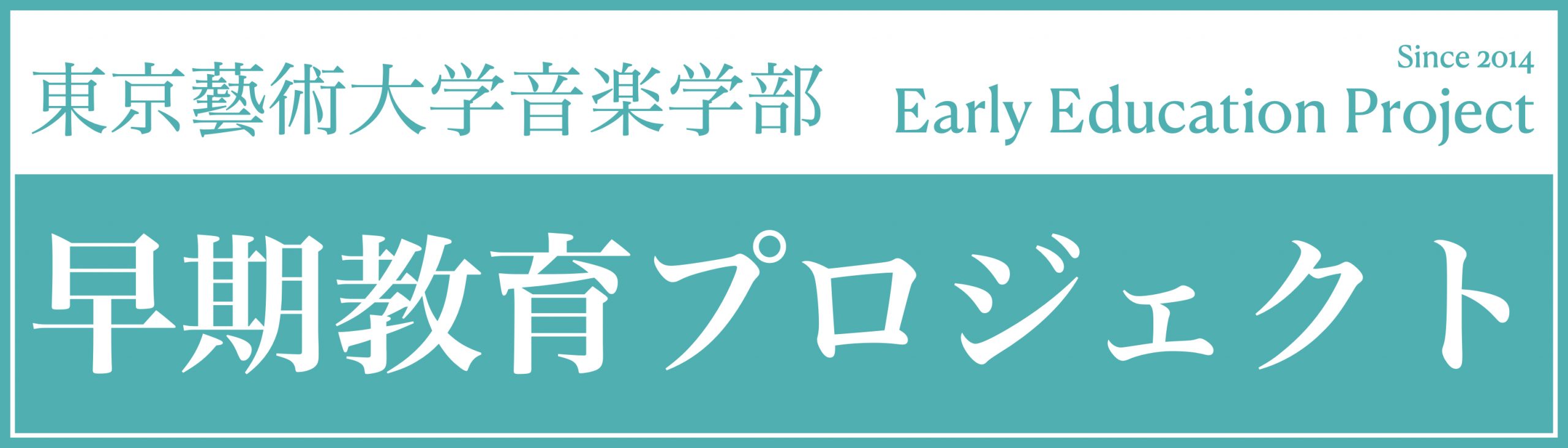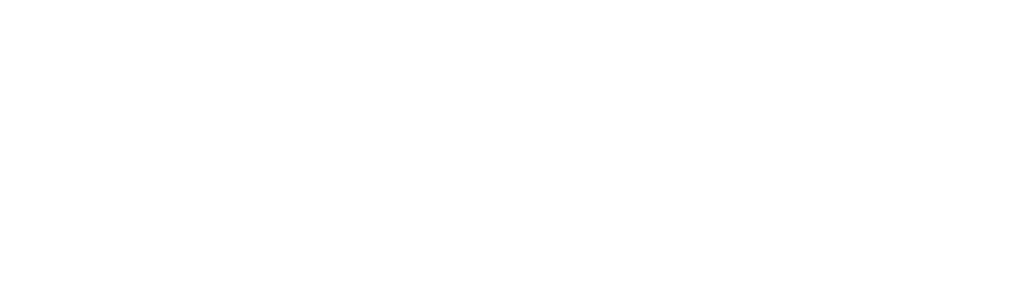- 大学概要
- 学部?研究科?附属機関?センター等
- 展覧会?演奏会情報
- 広報?大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般?企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十二回 光井渉「心機一転」
最近、京都に行くことが多くなった。だいたい月に2回くらい行っていると思う。
日本建築史と文化財保存を専門にしているので、実測調査や史料閲覧あるいは修理工事への関与といった用事で、以前からしばしば京都を訪れていた。しかし、文化庁が京都に移転した関係もあって、審議会関係の用事が増え、日帰りかせいぜい一泊で京都に行くことが断然増えてしまった。
性格上、入念に下調べをした上で、かなり緻密なスケジュールを設定して行動することが多いが、頻繁に同じ場所に行くようになると、会議の開始時間と終了時間だけを頭にいれて、用事が済んだらさっさと帰京するというパターンになっていた。
そんな折、いつものように京都に赴いたところ、予定よりもかなり早く会議が終わってしまった。このまま帰京するのは寂しいので、思い立って西本願寺まで歩き、阿弥陀堂(本堂?1760年)と大師堂(御影堂?1636年)をお参りすることにした。さぞインバウンドで賑わっているかとおもいきや、数組の家族が静かに座っているだけで、広大な木造建築の内部空間にゆったりと身を置くことができた。ほのかに輝く金色の内陣と頭上に広がる暗闇に、すべてが吸い込まれるような感覚を久方ぶりに感じることができたのである。
私の出身地は広島で、浄土真宗の門徒が多いことで有名である。そのため、幼いころ祖父と父に連れられて西本願寺に来たことがあり、阿弥陀堂の内部で正座して読経を耳にしたことを強烈に記憶している。この体験は、後に建築に進み、研究のメインテーマを江戸時代の寺院境内と建築に定めたことの遠因だったのかもしれない。近年でもコロナ禍の直前に調査していた富山県高岡市の勝興寺も浄土真宗の寺院である。この時の調査報告書では、論争が尽きなかった大広間の建築年代(17世紀中期)とその建設経緯を明らかにできた。そして、ここで明らかになった事項が、令和4年に勝興寺本堂及び大広間が国宝に指定される理由の一つになったことを、大変誇らしく思っている。
この3月まで美術学部長を勤めていた。任期中の3年間は、コロナの期間に様変わりしたキャンパスを元通りにすることを目指したが、電力料金問題以後に慢性化した予算削減の他にも事件が相次ぎ、心安らぐことは無かったように思う。この間、建築科の学生や研究室のメンバーとも十分な時間をとれず、申し訳ない気分でいっぱいである。
4月以降も、さして暇になったわけではないが解放された気分であることは間違いない。西本願寺での経験を糧にして、心機一転、本務の教育研究にカムバックしようと思う。現場が私を待っている。

勝興寺大広間から本堂を望む

勝興寺大広間
写真(上):勝興寺本堂
【プロフィール】
光井渉
東京藝術大学 副学長 美術学部建築科教授
1963年広島県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程中退。博士(工学、東京大学)。文化庁文化財保護部文部技官、神戸芸術工科大学助教授などを経て、東京藝術大学美術学部建築科教授。専門は日本建築史、文化財保存。著書に『近世寺社境内とその建築』(中央公論美術出版、2001年、建築史学会賞)、『日本の伝統木造建築 その空間と構法』(市ヶ谷出版社、2016年、日本建築学会著作賞)、『日本の歴史的建造物 社寺?城郭?近代建築の保存と活用』(中公新書、2021年)などがある。